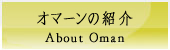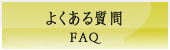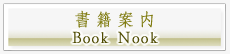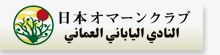3月, 2024年
4年ぶりにオマーン大使館で祝賀感謝会
 ようやく春めいて来た3月1日、「オマーン大使館祝賀感謝会」が4年ぶりに開催されました。
ようやく春めいて来た3月1日、「オマーン大使館祝賀感謝会」が4年ぶりに開催されました。
このイベントは、日頃から大使ご夫妻をはじめとする外交官の方々や大使館職員の方々には大変お世話になっており、日本オマーンクラブとして感謝をお伝えする場として2013年以来毎年開催して参りました。同時に大使館の皆様と会員同士の親睦も目的としております。
祝賀感謝会当日は、受付を済ませ「くじ」を引いて、「くじ」で指定されたテーブルへ参加の皆さんが向かわれました。各テーブルには、大使、大使館の方々、職員の方々がお一人ずつ同席をされ会員の皆さんと親交を深められるような配席となりました。
 司会は会員の半澤彰さんが務められ、何と日本語とアラビア語による司会で進んでいきました。オマーンクラブ会長のジョーンズ享子さんより開会のご挨拶で始まり、モハメッド・アル ブサイディ大使閣下のご挨拶のあと外交官の皆様と大使館スタッフが紹介され、クラブから大使館の方々に、感謝の気持ちを込めて記念品が贈られました。
司会は会員の半澤彰さんが務められ、何と日本語とアラビア語による司会で進んでいきました。オマーンクラブ会長のジョーンズ享子さんより開会のご挨拶で始まり、モハメッド・アル ブサイディ大使閣下のご挨拶のあと外交官の皆様と大使館スタッフが紹介され、クラブから大使館の方々に、感謝の気持ちを込めて記念品が贈られました。



(小画像はクリックすると拡大します。拡大してご覧ください。)
プレゼンターは理事の柴田芳彰さんと久保田郁子さんのお二人。大使ご夫妻への贈り物は、震災復興の願いも込めて石川県で作られている「九谷焼のデミタスカップ」(北斎の大波と赤富士のデザイン)を。外交官、職員の方々には「豆皿」が贈られました。皆さんとても喜んでくださり、4年のブランクが一気に無くなるとても温かな雰囲気となりました。そのあと、オマーン国を紹介するビデオが流れ、会員の皆さんはオマーンを訪れたいと思われたに違いありません。


各テーブルでは、オマーン国の世界遺産の多さ、豊かで美しい自然、日本並みかそれ以上に良い治安の話など様々な話で盛りあがっていました。しばらく歓談しているとお待ちかねのランチタイムです。
メニューは、大使館でお料理教室を開催してくださる大使夫人のアイシャさんが考えてくださったとのこと。残念ながら体調を崩されてしまい当日はご欠席でしたが、開催前日まで準備をしてくださったそうです。感謝の念に堪えません。
(小画像はクリックすると拡大します。拡大してご覧ください。)
お料理はメインホールの隣の部屋にセットされていました。今回のメニューは、
「アラビア風ドレッシングの野菜サラダ」「フムス」「ピタパン」「ババガヌーシュ」「アラビア香味の魚料理と肉料理」「チキンカレーや日本米のご飯やサフラン入りのお米料理」が出されていました。デザートには「パンプリン」や「デーツ」、もちろん定番のオマーンコーヒーには、カルダモンとローズウオーターが入っていました。彩も美しく、美味しくて、皆さん何度もおかわりに足を運ばれていました。






おなかも落ち着いて、コーヒーのおかわりも底をついたところ、大使が各テーブルを回られたり、会員の皆さんも各々のテーブルを離れ、自己紹介をしたり、写真を撮ったり、親睦を深められていました。









「宴もたけなわではございますが」と半澤さんのアナウンスがあり楽しいひと時も終わりに近づきました。閉会のご挨拶は、オマーンを誰よりも愛し、オマーンに尽力をされた、オマーンクラブ名誉会長の遠藤晴男さんでした。最後に1本締めで、4年ぶりの「オマーン大使館祝賀感謝会」が幕を閉じました。


あっと言う間の1時間30分でしたが、皆さん楽しい時間を過ごされたと思います。
いつもながら、大使館のスペースをご提供くださる大使閣下、準備をしてくださる大使館の方々、職員の方々に改めてお礼を申し上げます。
今回は51名の会員が参加されました。次回は更に多くの会員の皆さんとお会いできることを楽しみにしております。
講演会「2024年の中東情勢を考える」が開催されました
2024年2月28日、オマーン大使館の厳かな雰囲気の中、中東情勢を考察する講演が行われました。パレスチナの現状を解説する講演者は、東京大学大学院総合文化研究科の鈴木啓之准教授で、会場にはパレスチナ情勢に関心を寄せる多くの参加者が集まり、多少緊迫した雰囲気が漂っていました。
冒頭アルブサディ駐日オマーン大使の強いメッセージが紹介されました。「現在ガザ地区で起こっている事は許し難い」「平和という言葉と行動が伴わなくてはならない」との言葉は、中東情勢が世界的な課題であることを強く意識させられるものでした。
時代を遡り、100年前の第一次世界大戦中のインフルエンザ・パンデミックでの経験に触れることからご講演は始まりました。当時、志賀重昂は「これから世界の情勢は関ヶ原だ」と述べ、中東情勢を「世界的川中島」と表現し、白人と有色人の間の分断を懸念していました。イギリスによるヨルダンとパレスチナの分割から時を経て、2017年末にトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と宣言し5年後に対立が爆発したことなど、写真やVTRを交えながら中東の歴史的背景が詳細に語られました。
 その後、鈴木准教授はガザ地区の現状に焦点を当てられました。『10.7』ハマスのイスラエルへの空爆から約5ヶ月が経過し、イスラエル軍によるガザ民間の病院・学校・国連施設への攻撃が繰り返され、多くの犠牲者(ガザの死者3万人、負傷者7万人)が出ているなど、未曾有の人道危機が続いている現実が提示されました。加えて、国際社会や周辺国は足並みが揃っていないことに触れられ、グローバルサウスVS欧米の様相を呈し、国連安保理の決議が出来ず終結への道筋が立たない状況とのこと。
その後、鈴木准教授はガザ地区の現状に焦点を当てられました。『10.7』ハマスのイスラエルへの空爆から約5ヶ月が経過し、イスラエル軍によるガザ民間の病院・学校・国連施設への攻撃が繰り返され、多くの犠牲者(ガザの死者3万人、負傷者7万人)が出ているなど、未曾有の人道危機が続いている現実が提示されました。加えて、国際社会や周辺国は足並みが揃っていないことに触れられ、グローバルサウスVS欧米の様相を呈し、国連安保理の決議が出来ず終結への道筋が立たない状況とのこと。
また、鈴木准教授は人道支援の重要性についても言及されました。ガザ地区では、飢餓や感染症が蔓延し、衛生状況も最悪の状態にあると指摘されました。具体的には25万人が呼吸器疾患に苦しみ、安全な水さえも不足し10万人が下痢に苦しんでいる深刻な状況であることに加え、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への資金拠出停止(国連職員の『10.7』イスラエルへの空爆関与発覚による)により国際支援が絶たれる懸念を強調されました。
さらに、周辺への負の波及効果もあり、イスラエルによるレバノンでの戦闘の拡大や、イエメンでのフーシ派に対する米軍の軍事攻撃などが中東全体に更なる混乱を招いているようです。中期的な影響として、中東和平の前提の崩壊、中東世論の「揺り戻し」/米主導による「中東再編」の行き詰まり懸念が益々広がっているとのこと。鈴木准教授は、「この人道危機が早く終わって欲しい、停戦しなければもっと最悪を更新し続ける」と国際社会に停戦を呼びかける重要性を強調し、講演は警鐘と共に幕を閉じました。
講演後は大使館のご厚意で出されたコーヒーとデーツで、鈴木准教授を囲んでの懇親会へと続きました。